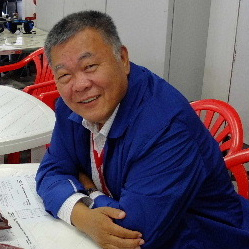2026年01月12日(月曜日)
01.12. 平和な日々。 三日前から写真が載せられなくなっています。
今、何も、何処も痛くない幸せで平和な日々です。
私は今、体中のどこも痛くない希少な時間を平和に過ごしています。
幼少の時から左足の変形がずーっと絶え間なく傷み続けて、
その痛さが慣れで無感覚の中に自覚しなくなっていても、
探せば、必ず見つかる種類の痛みで、普段は無に等しいのですが、
ふとした弾みで暫くの間、自分を支配されてしまう事もあります。
それが今、進行の中で痺れてしまって本当に無感覚になって痛くないのです。
ただ、
その無感覚の中に、
ピリッピリした痛みが時たま走って、ドキッと怯えるのですが、
すぐに消えてしまうので忘れてしまいます。
いつか分かりませんが、
いずれは、このピリピリが無につながってくる筈なので、
だから、多分つかの間だとは思うのですが、
今、私にとっては希少な平和の時間なのです。
平和であることは、すなわち幸せです。
しかし、私にとってはそれがたとえばちょっとした痛みであったとしても、
多くの人にとっては、
もっと耐えなければならない事がたくさん有って、
私の場合は、むしろ
大した方ではないと、よく思います。
それよりも、むしろ、外から得られる喜びの方がはるかに大きく、
充実した日々をずっと送ってきました。
ところが、今年の5月、腰から下半身にかけて強烈な痛みに襲われて、
本当に痛くて、何も出来ない日が続く経験をして、
たまにやってくる痛くない短い時間が
「平和」という言葉がぴったり合う幸せな時間と感じたのです。
だから、今、その痛みが収まっていて
痛くない時間が当たり前になっていると、
そのありがたみ、「平和」のありがたみも忘れてしまいそうになります。
しかしその内、また、あの強烈な痛みに襲われる恐れも十分にあって、
それを考えると、モタモタしていてはイカンと強く思うのです。
何か、突然死んでしまう事があったとしたら、
それは仕方がないし、逃げようがないと思うのですが、
その時に「あれはやっとけば良かった。」とだけは思いたくないので、
まだ何処も痛くなくて、
車イスでの不便はあるものの、
何でも出来る今、・・今、全速力でやらなくっては、と思うのです。
平和のありがたみは、戦争が好きな権力者・独裁者には絶対、理解出来ません。
また、彼らのようには、絶対になりたくないとも思うのです。
独裁者は、彼らが独裁者であるが故に戦争が大好きです。
そんな独裁者たちの戦争で死ぬのは、何よりも最悪でしょう。
少なくとも今の日本は平和であり、
少なくとも、
私が生きている間は平和であるでしょうから、
体も平和である今、本気で全力でやらなくっては。と思うのです。
Posted パーマリンク
2026年01月11日(日曜日)
01.11. 三連休の中日「成人の日」。ややこしい日。
三連休の中日。
明日の月曜日が何の休日かと思ったら「成人の日」らしい。
私達の頃の成人式は1月15日と決まっていたので、
1月12日が成人の日と言ってもピンと来ない。
しかも、「成人の日」は固定していず、三連休になるように移動するらしい。
しかも、
・成人が18歳にあり、
18歳で成人した若者は、
・社会人としての権利は1人前になるが、
同時に、・社会人としての義務も一人前になるという、
・しかし、飲酒喫煙は20歳のままで、
(オマケに、女性が結婚できる年齢は16歳から18歳になったという。)
そういった変化はあっても、
・当日に行われる自治体による式典の対象は20歳の若者で、
・式典の名前は「二十歳(はたち)の集い」というそうだ。
ややこしい。
「成人」つまり
「権利と義務の同時発生の年齢」を、
「20歳」から「18歳」に変更したことによって、
つじつまが合わない事が色々と出来たので、
そこを一つ一つ調整しても、変えられる事と変えられない事があって、
ややこしい事になった。
ややこしいついでに三連休を増やす工夫までした。
ついでに男女平等をひとつ解決して、
それにしても、飲酒と喫煙は20歳のままにしたのは意義がよく解らない。
ややこしくなったので、前は、成人の日に成人にお祝い金を出していた筈だが、
今年は間に支払い稟議が何も来なかったが、止めにしたのだろうか。
何も来なかったという事は、逆に、出し続ける=変更なしという事だろうか。
(たぶん、そうだろう)
大昔、会社から福利厚生としてのプレゼントとしては、
クリスマスイブに、社員の子供(小・中学校)に
KeePerサンタとしてプレゼントを贈っただけだったが。
(これは今も続いているそうだ)
今は、色々あるらしい。
その恩恵の一つぐらい私の所にも来て良さそうだが、もちろん何もない。
この会社とKeePerが持っているポテンシャルの最大化を実現する為の障害は、
今現在でのKeePerの成功のおかげで、
それぞれが成功者になってしまい、
自己否定できず、進化出来ないでいる事だと書いたが、
その筆頭が私自身であることは言うまでもない。
自分が一番、たぶん自分に自信がないから、
若い時から誰よりも休もうとせず、沢山働き、沢山出張もした。
誰よりも朝早く出勤していたこともあった。
誰よりも一番本も読んだ。
しかし、それは今考えてみると、
自分に自信を持っていないが故の、代替え行為だったのかもしれない。
それすらもなく自信だけ持つ困った者もいるが、
それは、それ故に破綻も早々に来る。
などとゴロゴロ考えながら
昨日も今日も仕事もせず、暇な時間を過ごす。
知多半島の先にある「おさかな広場」に行った。
近くの観光客がいっぱいいた。
トリミングに行ってリンダが、
冬なので、あまり短くすると寒くなっていけないからなのか、
あまり毛が短くなっていなかった。それを見て、
なんか損したような気がしたのは、私の肝っ玉が小さいからでしょう。
午後からは「全国女子駅伝」を見てから「大相撲 初場所」を見ました。
平和な一日です。
昨日から、何かのメモリーがいっぱいになってしまったのか、
写真が貼れないようになっています。
私にはどうすればいいのか全く分からないので、
明日まで、写真無しで投稿します。
明後日、会社に行ったら誰かに直してもらう事にします。
それまで写真無しです。
Posted パーマリンク
2026年01月11日(日曜日)
01.10. ポテンシャルを最大化するために、何を、どうすべきか。
今、全国のすべてのKeePer LABO店から、
「〇〇店2026年12月へのメッセージ」が、添付されたメールが来ます。
2025年12月、つまり終わったばかりの12月と年末を振り返って、
やった事、やれなかった事、良かった事、反省すべき事、
そして今度の1年後の年末、
つまり2026年12月には、ああしようとか、こうしようとか、
2025年の12月が終わった今の時点で、
1年後の今度の年末には実行すべきだと思った事を
次の12月へのメッセージという形で書き残しておくのは、すごく意義がある。
特に、
反省すべき事を書き残して、
あるいは良かった事を書き残しておいて
次に活かそうという事は正に学習であり、進歩の為に一番大切な部分です。
反省とは、つまり、過去の自己否定に他ならず、
進歩につながる。
こんな所がKeePer LABOの強さの原点なのかも知れません。
特筆すべきことは、この習慣がいつから始まっているのかは忘れたが、
少なくとも私が指示したことではなく、いつの間にか始まっていました。
仕事は誰かの命令によってやらされていると、
自分の100%の力は発揮出来ません。
出来ないというよりも力を出さないものです。
やらされているだけなので、
余力が残っていてもそれを出す必要がないからです。
扱っている商品の力を、
例えばKeePerの力を100%発揮させる為には、
KeePerの施工技術を十分に身に着ける事に加えて
その技術を発揮して
車をキレイにする動機を自分の中に持っていなければなりません。
その動機とは、
お客様と共有した「この車をこんな風にキレイにしたい」の気持ちで、
上司からの命令でもないし、売り上げの為でもなく、報酬の為でもありません。
自らの心に湧き出た、お客様と共有した動機です。
と言っても、高尚なものでも何でもなく、
ごく普通にお客様と気が合ったり、共感したり。
そういう
自然な動機は、
上司などからの「やらされる動機」に比べて、
はるかに強く、精度の高い動機で、サービス業には欠かせない要素です。
だから、
KeePer LABOにしても、多くのKeePer PRO SHOPにしても
ここが出来ているケースが多いので
ここまで強くなっているのでしょう。
KeePerの強みは、
製品そのものの優位性と、
技術を広める事が先行するビジネスモデルもあるが、
このお客様と店側が動機を共有する事が、実は、圧倒的な強さを出しています。
こういった要素が、KeePerの今を造り出しているのだが、
その可能性を100%引き出されているかと言えば、否というしかない。
現在、KeePer LABOが167店舗、
技術認定店KeePer PRO SHOPが6,648店舗、
それに加えて、全国の新車ディーラー、KeePer施工店が多数、
更に、まだほんの少ししかないが、家庭用のKeePerを扱う業者さん、
もっと少ないがDIY用としてKeePerが利用されている。
これらが総合してKeePer LABOの信頼が形成されている。
しかし、
KeePerと、その仕組みと、
マインドが持っている価値の本当の可能性・ポテンシャルが、
今の、その何倍もある事は、私自身がよく分かっているつもりです。
しかし、
その可能性を100%実現するには、
私達の発想力と実行力、能力だけでは到底足りないことも
よく分かっています。
特に、今の状態に満足してしまって。
自分の力量と能力が足りないので現状でしかない事に気が付かず、
かつ、今の自分を肯定する狭い枠から抜け出せず、
今の自分を否定しないでいる者達では、
今の状態からジャンプする事は難しいだろう。
そこを脱出する為して、
最大のポテンシャルを実現する為に
何を、今どうすればいいのか。
多くの皆さんに喜んでいただくには、今、何をどうすればいいのか。
Posted パーマリンク
2026年01月09日(金曜日)
01.09. 与えられた時間が有限である事。
当然の事ではあるが、人も生物なのだから与えられた寿命は有限です。
しかし、中国の権力者が、
現代の医学は発達しているので
「臓器移植を繰り返せば150歳まで生きられる。」
と言い、
自権力へのあくなき執着を見せた。
他人の臓器を次々と自分に移植して、
体は他人になっても、意識だけは自分になってでも長生きをするという。
彼は完全に自分を神だと思っているようだ。
それはロシアやアメリカの権力者達も同様で、
本気で自分を神だと思っている。と、思われる。
これは、普通の会社でも、
自分が「長」が着く役職になると
権力者になったような気になるのと大して変わらないのだろう。
そんな人は、
潜在的にはものすごく多くて、
ひょっとして見方によっては、すべての人なのかもしれない。
いずれにしても生き物の寿命が有限であることには変わらない。
だからこそ、
自分の遺伝子を半分持っている子供に承継する事によって
それが自分とは全く違う別の人格であるにもかかわらず
自分の生が延長しているような気になる。
しかし、私は若い時に、
そうされるのがイヤで起業していきさつもあって、
自分自身がそうしない事は間違いない。
子供が、遺伝子の半分が自分と同じであっても、
自分とは全く違う人格である事は、
良い意味でも、悪い意味でも明白です。
家族は、家族ではあるが家族以外の何物でもなく、
あくまでも人格として自分ではない。
話を戻して、
いずれにしても、
生き物の寿命が有限であることには変わらない。
だから、
どんどん新しい事をやって行かないと、
時間が限られているのに、何も新しい事をやれない事になる。
時間が限られている。
限られた時間の中で、思いっきりいっぱいの事を見たいし、やりたいし、
限られた時間。勿体なくっていつまでもダラダラ同じことをやっていられない。
今日から「オートサロン2026」
今回の展示車は、
石浦選手から、開発中のGRヤリスと、
LABO女子スタッフの十数年前の180SX黒。
どういう組み合わせなのかと言えば、誰もよく分からない。
いずれにしても、
面白ければそれでいいと皆が思っているのは、いかにもKeePerだ。
来月オープン予定の2軒のKeePer LABO。
直営店が一軒と、
FC店が一軒、
しばらくお待ちこのペースが続いていく。
が、来年はその比率が2:1になる。
もちろんFC店2に対して直営店1の割合だ。
それで、だんだんこのペースが上がって行って、
5年後には、FC店250店 : 直営店250店になるはず。
これからどんどん面白くなって行きます。
Posted パーマリンク
2026年01月08日(木曜日)
01.08. 昔はこの時期、よくグアムに行って遊びました。
年末のほとんど必死とも言えるような激闘の後、
1月、2月は、12月の半分くらいの売上げになります。
12月がほとんど平月の1.6倍お客様が来られるので、
1月と2月がそれぞれその半分、平月の0.8倍✖2か月です。
だから1月と2月にかけて、みんな、それぞれ交代で1週間休みを取ります。
有給休暇も使って、長期で海外旅行に行く者も多くいます。
この時期は、
遊びに行った先でサービス業の人が多くいます。
私は、この時期、よくグァムに行って遊びました。
働く時は思う存分、お客様の為に働く。
遊ぶ時も思う存分、自分と自分の家族の為に遊ぶ。
これはオマケ。トリミング前夜のリンダ。
今日、LABOの皆に一斉メールを送りました。
—————————————————————————-
みなさんへ
お正月が終わり、新しい年の運営が始まっています。
年末に激しく来られたお客様は、この時期に来られる訳がありません。
今の時期は、皆さんがしっかりと休暇を取る時期です。
メリハリ良く、しっかりと休暇を取らなくてはいけません。
1週間の休暇は勿論、
それぞれが持っている有給休暇を使って、
もつと大型の休暇を取ることも必要です。
人時生産の数値が著しく落ちるようなだらしない営業は、
店舗にとってもスタッフにとっても
害毒でしかなく、運営責任者の運営能力の欠如と言わざるを得ません。
12月のせっかくの素晴らしい実績を上げた店舗であっても、
そんな店舗は、残念ながら評価を下げざるを得ません。
それぞれの部長、副部長、地域担当、全店の店長、
メリハリの効いた運営をお願いします。
今の時期は何処に行っても空いていて、この時期に休暇を取れる事は
サービス業の特権です。
私も昔はこの時期の特権を生かしてよく遊びました。
谷 好通
Posted パーマリンク