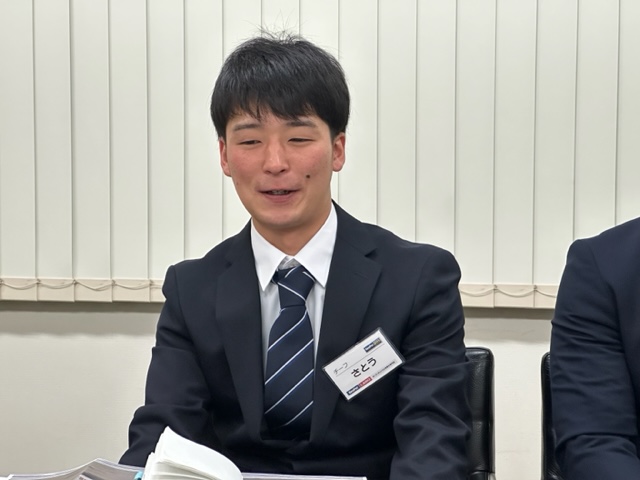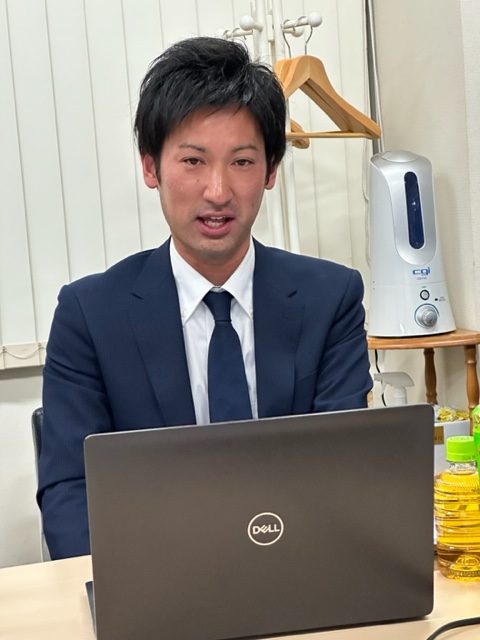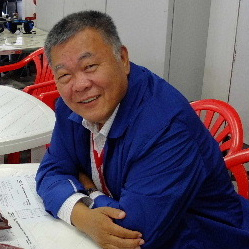2024年03月16日(土曜日)
03.16. 朝からトレーニングと病院、のち店舗プラン会議。
私は週二回、レストレーションというトレーニングを受けています。
「レストレーション【restoration】」とは、
インターネットで調べると回復、復興、復古などと書いてあるが、
「レストア」を表す意味が
元の状態に戻すこと。復元すること。
特に、古くなって傷んだ自動車や家具などを修復すること。
とあり、「古い車をレストアする」と言えば、
その行為を「古い車のレストレーション」となり、
だから私が受けているレストレーションとは、
ガタが来ている私の体を鍛えて復元しようとするトレーニングであって、
けっこうキツイ。
だから、よっぽどもうやめようかと思うのですが、
ここでやめたら、
すでにガタがきている私の体が、
加速的にガタガタになって行くことは目に見えているので、
すごく仕方なく頑張っているのです。
1時間のプログラム(実際にツライのは30分ぐらい)を終えると、
私の場合、回復に30分くらいかかる。
だから今日も、レストレーションを終え、30分以上過ぎてから病院に行った、
今日の病院は左足付け根に出来た腫物の切開。
痛かったというより、ハラハラであった。
そんなことをやってからの、午後の店舗プラン会議は真剣そのものです。
特に、最初の議題は
フランチャイズの店舗で、社長まで来て店舗のプラン作りに加わり、
真剣に検討する。今日は第一段階の大体のプランを出して、
一度図面に落としてから、法的な摺り合わせと共に
その図面を基にプランを詰めて行く。
一軒に対して、3回から4回はみんなで検討しつつ工事まで固めていく。
そして何軒かの、何段階かの軒数のプランを詰めて行き、
実際に工事が始まって出来上がる寸前にも看板類の検討をする店舗もある。
今日は、複数の新店のプラン出しと、
4月にオープン予定のLABO福岡春日店の看板の詰めをやった。
全面改装の工事で休業中のLABO福岡春日店は、
まだ看板の確認で変更がありましたが、もうすぐオープンです。
もう一つの大改装は、
年が明けてからドライブスルー洗車機を撤去したKeePer LABO小平店。
大好評で、その売り上げも大きく店舗に貢献していたドライブスルーは、
洗車待ちの行列が道路に大きくはみ出し、近所に迷惑をおかけしていたので、
泣く泣く撤去に踏み切った。
それを補って余るだけの価値を店舗に作りださなくてはならないので、
この大改造には何回もの議論と検討が重ねられ、どうにかここまで漕ぎついた。
間もなく着工する。
夕方まで気の抜けない、充実した土曜日の今日。
でも、いつもの、普通の土曜日です。
Posted パーマリンク
2024年03月15日(金曜日)
03.15.相手をよく知る事。相手に伝える事。率直に伝える事。
今日は午前中にLABO用賀店に行って、
香港から来られている大きな投資家に1on1のIRとTREXKeePerの見学。
まず朝一で専務とCFOにインタビュー、次に社長にインタビュー、
最後に私にインタビューで、後からみんなに聞いたら、
質問の内容は、みんな同じだったそうだ。
同じ質問を会社の主要メンバーにして、
返ってきた答えがバラバラであったら、この会社はバラバラであって、
コミュニケーションすら取れていないという事であり、
将来に多分に不安があるという事であるようだ。
特に私がインタビューを受けた時はすべての答えが一致していたようで、
問題なかったのだが、これはすごく面白いと思った。
よく、会社の中のコミュニケーションは、まず飲みにケーションからと言って、
お酒を飲みながらのコミュニケーションが大切だと言われますが、
この会社の役員は、ほとんど一緒にお酒を飲む機会はありません。
外部の方とのお食事の席ではこちらの役員も揃っていて、
結果的にお酒を飲むことにもなりますが、
その他には、身内の幹部だけで酒を飲む機会はまず皆無でしょう。
会社が終わったら、みんなバラバラに次の出張先に飛んで行くか、
現場の達成会に行くか、
私はあまり食べられないので(カロリーオーバー)、
90%以上の確率でそのまま帰宅してしまう。
しかし、仕事中にずいぶん話をするし、話をすれば真剣に話す。
報告もだいたいリアルタイムでお互いにする。
お酒を飲む機会には却って仕事の話は出ないし、
しても、バカ話の類ですぐ忘れる。
それで、十分のコミュニケーションは出来ていて、
お互いの認識のズレはほとんど無いと言っていい。
だから今回のようなケースでも、当然の結果であって意外でも何でもない。
むしろ彼らの助言・意見が、みんなすごく興味があって熱心に聞いた。
投資家は成功している会社、今後成功する会社を見出して投資しているので、
彼らの意見は、ものすごく実践的であり、
実務なく成功体験もない人の机上の空論より100倍もためにるのです。
厳しいですが、私はこの人たちの言葉を真剣に聞きます。
この会社の為に。
自分自身の為にも。
この有意義な時間の後、東京営業所・トレセンのある三郷に向かいました。
しかし、今日の東京近辺の道路は異常なまでに交通量が多く、
始めから終わりまで渋滞で、
普段は30分のところを1時間半もかかってしまいました。
もう店長会が始まっているのは分かっていて、午後3時前、
腹が減って・・牛丼の吉野家に寄ってしまったのです。
東京営業所の近くの最新型の吉野家。
腹が減っていたからなのでしょうか、めちゃくちゃ美味かったのです。
しかも驚いたのは、
注文を注文カウンターで、対面で、スタッフにするのです。
その上で、料理が出来上がり
持ちされたベルが鳴ったら、自分で料理を取りに行くシステムです。
注文の時点でスタッフと客はコミュニケーションがあるのです。
これはスターパックスと同じ方式です。
他の牛丼屋では、
自動券売機で、食券を買う段階で自分で料理を選び、
出来上がったら、料理をスタッフが持って来ます。
料理を持ってきたスタッフとのコミュニケーションは、当然、ありません。
吉野家の新しい戦略はどの時点でのコミュニケーションが意味を持つのか、
スターバックスから学んだのではないでしょうか。
注文を受ける所でのコミュニケーションがポイントです。
これって、実はKeePer LABOと一緒なのです。
しかも、吉野家の新しいメニューは、本当に美味しく(腹が減っていたから?)。
私はこの時点で、この業界の中での吉野家の勝利を予感しました。
東日本店長会では、喋りすぎるぐらい喋ってしまいました。
いろんな思いが巡り、たくさんの事が頭に浮かんできて、
いっぱい喋ってしまいました。
喋り過ぎて、本当に良かったのかどうか心配ですが、
喋ってしまったので、仕方ありません。
帰りは、
いつもの夕陽です。
東京駅にたどり着いて、驚き、笑ったのは、
東京駅のシンボルになっているテントが、桜色にライトアップされていたのです。
本気で笑っちゃいました。ホントにいよいよ春になったのですね。
Posted パーマリンク
2024年03月15日(金曜日)
03.15.出張が平気で出来るようになっている自分に驚く
朝、7時前に家を出て、今、新横浜に向かって新幹線に乗っています。
昨日は、午前中から昼にかけて大切な仕事を事務所でして、
午後LABO京都店で行われている西日本LABO店長会に出て、
いっぱい喋って、
夜、帰ってきました。
普通は乗っている車の中でパソコンを開き、仕事をしたりするのですが、
昨日は頭の中でいっぱい考え事があって結局パソコンを開かずのままでした。なので、家に帰ってから食事をして間もなく寝てしまい、
何年振りかのこのコラムを三連休です。
一昨日は中日本LABO店長会。
今日は三郷で東日本LABO店長会です。
その前に、午前にLABO用賀店でTREX見学のリクエストに応えたIRがあり、
今、新横浜に向かっている訳です。
来週は東京に一回と熊本に一泊の出張がありつつ、11回のIRがあります。
しかも、1つはスモールミーティングで、
二桁の複数の機関投資家の皆さんが東京でお会いします。
もちろん、こんなことに加えて、日常の業務がこれ以上にあります。
何を言いたいかというと、
私はこんなにもいっぱいの仕事が出来るようになったということです。
しかも、一昨日とその前日には、
ざっくばらんの人達、仲間達との飲み会で楽しく騒ぎました。
二年前までの三年間のしんどかった日々と比べると
本当に嘘のように元気になったのです。
しかし、出張が出来るようになっただけで、
出張をすれば移動時間が費やしてしまい、仕事量は却って減る事になるので、
出張が出来なかった時に比べて仕事量そのものは変わらないのですが、
出張が出来るようになると、実際にお会いしての仕事になるので
仕事の中身の濃さが変ってきます。
やはり、今の方が充実します。
しかし、
「宿泊」はやっぱりすごく苦手で、
月に一二回しかしなくなっています。
風呂がダメなのです。
体調とは別に左足の不自由(変形)が進行していて、
装具無しでは立っていられなくなっていて、
自宅の風呂は手すりが必要な所に複数付けてあるのでいいのですが、
ホテルの風呂にはとても危なくて入れません。
しかも家の風呂には「お風呂KeePer」が掛けてあって滑らないのですが、
ホテルの風呂はツルツルで、怖くて入れません。
だから、東京で二日続けて仕事があっても、
時間的に許されれば、東京に泊まらず、いったん名古屋に帰ってきます。
しかし、それでも仕方なく東京に泊まらざるを得ない時には、
私は風呂に入っていません。シャワーも浴びていません。
だから、昨日は京都から直接東京には行かず、
無理して早起きして、今、新幹線に乗っています、
しかし、おかげで、
美しい富士山の姿が見られたのは、めちゃくちゃラッキーでした。
Posted パーマリンク
2024年03月13日(水曜日)
03.13.二日連続でお酒を飲んでしまいました。・・二日連続お休みです。
昨日は、定例会でお酒を飲み、
今日は、懇話会でお酒を飲みました。
私は今、滅多に外食する事が無くなっているので、
二日連続の外食と飲酒、これは珍しい事なのです。
だから、
今月は、一日も休むことなく続いたこのコラムも
ここに至って、酒を呑んで酔っ払ってしまったので二日間連続のお休みです。
たまのことなので、ご容赦を。
Posted パーマリンク
2024年03月11日(月曜日)
03.11. 新店2軒、LABO熊本長嶺店とLABO宇都宮店のキックオフ。
今日3月11日は13年前、東日本大震災が起こった日。
2軒の新店KeePer LABOのキックオフミーティングがありました。
まず、熊本のアイビー石油さんが既存店LABO青葉店を閉めて、
地元熊本にオープンする純LABOのKeePer LABO熊本長峰店。
熊本市の長嶺地区の絶好の好位置に、絶好の居抜き物件を探し出し、
最小限の投資で、ほぼ理想的なKeePer LABOを構築する。
何度も貸して欲しいと言った私の懇願を振り切って自前で運営する。
完成予想パース
初めて夜景で造って見た。
ありぞのさん
みやた君。
LABO西隈本店で立派な成績を造り上げた濵崎店長。ご存じハマちゃん。
若き日の同志馬場社長。63才になったそうだ。
当然だが私と同じペースで歳を取った。それにしても酒が好きだ。
もう一軒は、北関東の大都市「宇都宮市」に出た物件で、
KeePer LABO宇都宮店。
350坪もの広さがあったので、
LABOフルスペックと
宇都宮トレーニングセンターを併設する形でオープンする。
北関東のマーケットは底知れずなので、今後、複数のLABOが造られて行く。
高い需要を考慮に、最初から5名体制での出発です。
ヨウレイ菌感染明けで、意外に元気な安藤副部長。安心しました。
ふくだ君。
おおもり君。
リーダーシップを求められる はらさん。
さとうチーフ
元小山店店長の、LABO宇都宮店の新伊藤店長。
地区担当の長谷川M
Posted パーマリンク